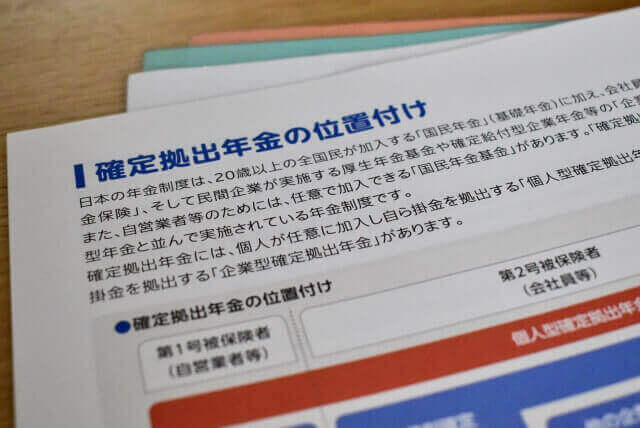制度を入れて終わりになっていませんか?
企業型確定拠出年金(DC)を導入して、説明会も実施して、ひと安心。
でもその後、従業員の多くが「とりあえず定期預金のまま」という状態になっていませんか?
じつは、企業型DCを利用している従業員のうち、約8割が元本確保型商品(定期預金など)に偏った運用をしていると言われています。
せっかくの制度があっても、活用されないままでは「宝の持ちぐされ」になってしまいます。
老後のための仕組みが、ただ積み立てるだけの箱になってしまっているのです。
企業型DCは導入して終わりではありません。
むしろ、導入後のフォローこそが本番、ここからスタートです。
ここをどう支えるかが、従業員の未来、そして企業の価値を大きく左右します。
導入時の説明だけでは不十分
多くの企業では、導入時にしっかりと説明会を開かれます。
ただ、その「一度きりの説明」で、すべてを理解して活用できる人は、ほんの一部です。
数ヶ月後には忘れてしまうのが現実
制度の仕組み、運用商品の選び方、リスクとリターンの考え方…。
導入時にはたくさんの情報を一気に説明されます。
でも、投資の経験がない人にとっては、理解するだけでも大変。
3ヶ月もすれば、ほとんどの内容は忘れてしまうのが現実です。
そして、よくわからないまま「安全そうだから定期預金でいいか」となってしまう。
これが、よくある「もったいない放置」のパターンです。
デフォルトの設定が元本保証タイプの預金になっていることが多いので、「預金でいいか」だけでなく、「わからないから放置」も自動的に預金となっています。
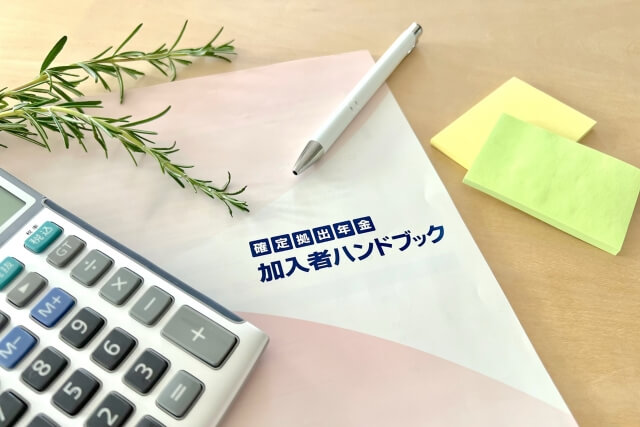
放置で広がる「将来の差」
例えば、毎月2万円を30年間積み立てた場合
- 定期預金(年0.01%):約720万円
- 年3%で運用:約1,160万円
- 年5%で運用:約1,660万円
同じ金額を拠出しても、運用次第で900万円近い差が生まれます。
これは、個人にとっても、企業にとっても決して小さくない差となります。
制度を「活かすかどうか」で、未来の安心度がまるで違ってくるのです。
デフォルト設定の預金で運用した場合でも、DC導入前の退職一時金とほぼ同額を準備できるようでしたら、大きな問題はないかもしれません。
ある程度の利率で運用しないと以前の退職一時金の水準に届かないのであれば、放置していると大変な状況になります。
継続的な投資教育が企業価値を高める
「投資教育」というと難しく聞こえますが、要は従業員が制度をちゃんと使いこなせるようにすることです。
それは企業の価値を高める行動でもあります。
定期フォローの積み重ねが大きな差に
導入から半年、1年と経つうちに、「あのとき聞いたけど、結局どうすればいいんだっけ?」という声が必ず出てきます。
そこで年1〜2回のフォロー研修を設けると、理解度がぐっと上がります。
効果的なタイミングとしては
- 運用開始から半年(初めての振り返り)
- 年度末(1年の運用を確認)
- 市場が大きく動いたとき(不安を放置しない)
- ライフイベントがあったとき(結婚・出産・住宅購入など)

世代別・立場別にアプローチを変える
20代・30代には「長期投資と複利のチカラ」
40代・50代には「見直しと受取設計」
管理職層には「マッチング拠出の活用と節税効果」
同じDC投資教育でも、伝える内容を変えるだけで理解が深まり、行動につながります。
「将来を一緒に考えてくれる会社」という信頼
継続的にフォローしてくれる企業に対して、従業員は「自分の将来をちゃんと見てくれている」と感じます。
それが満足度を高め、結果として定着率や採用力の向上につながっていくのだと考えます。
つまり、投資教育は福利厚生の一部であると同時に、企業ブランディングの一部でもあるのです。
全国のFPと話をする機会がありますが、そこで、出た会話です。
都市部の企業ですが、就職説明会で「会社でライフプランなどの研修、相談ができるのか?」という質問が出るようです。キャラプランもあると思いますが、若い世代は真剣に将来のことを考えていますし、不安も大きいのだと思います。
福利厚生での重要なポイントは、給与、休日、有給休暇は当然のもので、さらにFP相談ということなのでしょう。
効果的な投資教育を実現するには
オンラインと対面、どちらも活かす
オンラインなら全国の拠点をカバーでき、録画配信も可能となります。
一方で、対面は双方向での理解が深まりやすく、質問もしやすい環境です。
理想はハイブリッド型。
基礎講座はオンラインで、個別相談や実践的なテーマは対面で。
それぞれの良さを活かすことで、全員が参加しやすくなります。
よくある質問TOP3
Q1:「どの商品を選べばいいの?」
→ 年齢やリスク許容度に応じた基本パターンを紹介。若い方は株式比率高め、中高年層は安定型などという考え方をお伝えします。
Q2:「市場が下がったらどうすれば?」
→ 長期投資の視点を持つこと。下がった時期はむしろお買い得と言えます。焦らないことが大事です。
Q3:「マッチング拠出はやった方がいい?」
→ 税制メリットを説明したうえで、家計に無理のない範囲で取り組む。投資は続けることが何より大切です。
外部専門家(FP)を活用するという選択
人事担当者がすべて対応するのは大変です。
外部のファイナンシャルプランナーを活用すれば、最新情報を反映した中立的なアドバイスが可能になります。
- 専門的な内容をわかりやすく伝えられる
- 個別相談にも対応できる
- 担当者の負担を軽減できる
従業員も「専門家に聞けた」という安心感を持てます。
研修、勉強会、個別相談など、どのようなサービスを従業員の皆さまに提供できるかは、ファイナンシャルプランナーと打ち合わせをしっかりすることで柔軟に設定できます。

企業が確認しておきたいチェックポイント
商品ラインナップは最新ですか?
古い商品や手数料の高いものが残っていないか。
見直すだけで、従業員の成果が変わることもあります。
運用状況を見える化していますか?
定期預金比率が高すぎる、年齢別に偏りがある、、、
全体の傾向を把握することで、次の教育テーマが見えてきます。
マッチング拠出、ちゃんと伝わっていますか?
導入していても知られていないケースが意外と多いです。
税制メリットを丁寧に伝えることで、利用率が上がります。
退職・転職時のフォロー体制
放置すると自動移換され、手数料がかかり続けることも。
退職時にはiDeCoなどへの移換を案内し、スムーズな引き継ぎをサポートしましょう。
まとめ:DCは「導入後こそ価値を発揮する」
企業型DCは、導入して終わりではなく、運用を育てていく制度です。
継続的な教育とフォローを通して、従業員の未来を支え、企業としての信頼を育むことができます。
投資教育はコストではなく、人への投資です。
「従業員を大切にする会社」というブランドを育てるための一歩です。
今こそ、制度を活かす企業へ。
従業員の安心と企業の未来、どちらも豊かに育てていきましょう。
従業員向け投資教育セミナーのご相談を承っています
企業型DCの教育・フォロー体制を整えたいとお考えのご担当者さまへ。
- 対面・オンラインの両対応
- 企業規模や年齢層に合わせたカスタマイズ設計
- 基礎から応用、個別相談までワンストップ対応
- 初回相談は無料です
従業員が「投資って怖くない」「やってみよう」と思えるきっかけづくりを、ぜひ一緒に取り組みましょう。
Wrote this article この記事を書いた人
福田 智司
▶独立系ファイナンシャルプランナーとして、相談業務、セミナー講師などで活動しています。 ▶FBCラジオ ラジタス 第一木曜日 10:50~ 「FPふくちゃんのお金に関するエトセトラ」レギュラー出演中 福井で唯一?のラジオFPです ▶FPでIFAというポジションを活かした相談が得意 節約だけが家計見直しじゃない!を念頭に置いた相談を心掛けています。 ▶法人向けに企業型確定拠出年金の導入サポートを推進しております